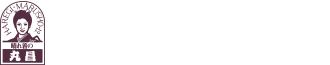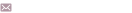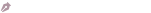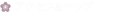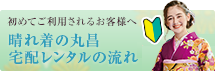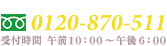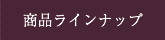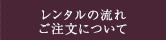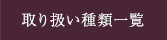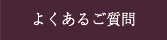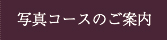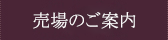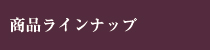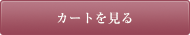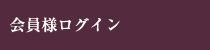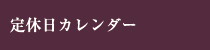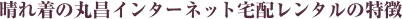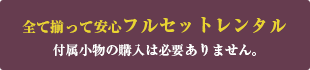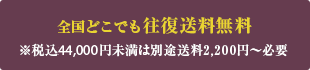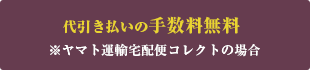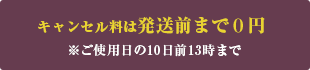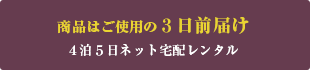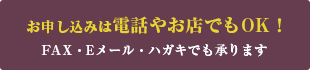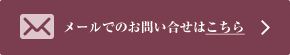- 晴れ着の丸昌 池袋店 TOP >
- 小紋

小紋
外出着として普段使いできる小紋はレンタルがお手軽です。柄のデザインによって幅広く活用でき、お稽古や観劇、友人との食事などいろんなシーンで楽しめます。
おしゃれな小紋で品格のある着こなしに
気軽に街着として楽しめる小紋。その多くが型染めという柄付けの技法で作られており、全体的に同じような模様が繰り返されているのが特徴です。柄も多種多様にあり、沖縄地方独特の染めである紅型や、紬に小紋柄を染めた柄。他にも、絞りや個性的な更紗、シックな縞模様、無地に近いものなどシーンに合わせてチョイスできます。素材が上質感をよりいっそう引き立てます。
いろんなシーンで楽しめるお洒落着の小紋
小紋は気軽に楽しめるレンタルがオススメです。お子さまのお祝い事や趣味、パーティなど、カジュアルからセミフォーマルまでしとやかな魅力を演出。個性的な柄からシックな柄まで、洗練された雰囲気を醸し出す小紋が揃っているのでイメージに合う着物がきっと見つかります。帯や小物のアレンジ次第でいろんな表情を楽しむことができます。カジュアルなテイストで選ぶなら細帯とも呼ばれる半幅帯や名古屋帯がおすすめ。格式のある席では箔を使った帯に、袋帯を合わせると上品な雰囲気になります。
小紋には訪問着や色無地とは違い、気をはらずに着られる外出着としての魅力があります。ただ、外出着とはいっても、着物の格など注意しなければいけないポイントがあるのも事実。
たしかに、小紋の格式は他の着物に比べ低いため、フォーマルな場には不向きな着物です。しかしその分、たくさんの着物の中で、堂々とおしゃれ着として着ることができる唯一の着物でもあります。
ここでは、おしゃれ着としての小紋の特徴と種類、楽しみ方についてご説明していきます。
小紋の柄や生地の特徴

小紋は着物の全体に同じ模様が上下方向に繰り返し描かれているのが特徴で、着物全体に柄が入っているのが総柄。部分的に繰り返し柄が入っているのが飛び柄です。
また、小紋に使われている生地は綸子(りんず)や縮緬(ちりめん)、紬など正絹が主ですが、現在では、木綿をはじめ洗える小紋としてポリエステル素材のものなど幅広い生地が使われています。
綸子や縮緬、紬など正絹で作られているものは、江戸小紋や京友禅、加賀友禅など華やかなに染められたものが多いのが特徴。木綿やポリエステル素材のものは、紺絣にシックな飛び柄を配置したものや、現代風なモダンなデザインが魅力です。
特に木綿やポリエステル素材の小紋は、普段着感覚で着るおしゃれな着物として人気があります。
カジュアルを楽しむ小紋
ドレス感覚で着ることのできる小紋は、カジュアルな席であればほとんどの場所に着ていけます。
レストランでのお食事会や同窓会、観劇などは正絹の小紋がおすすめ。
柄も色鮮やかで華やかなものが良いでしょう。合わせる帯は箔や錦織りの名古屋帯。
お花や趣味のお稽古には木綿や絣のものがシンプルで爽やかな印象を与えます。
帯は半幅帯やシンプルな柄の名古屋帯を合わせましょう。
また、普段着で着る小紋は格子柄や縞柄、花柄など飽きのこない柄を選ぶのがポイント。
帯は結びやすい博多織や紬の半幅帯などがよいでしょう。
小紋と相性の良い帯
小紋には名古屋帯や半幅帯を合わせるのが一般的ですが、小紋の柄や生地によって合わせる帯も変わってきます。
たとえば、小紋にも柄によっては訪問着とみまちがう豪華な着物もあるため、そんな時は品格のある袋帯を合わせることも。そのため、小紋と帯の相性は着物の柄が生み出す品格に合った帯を選ぶのがポイントです。
しかし、小紋はあくまでもおしゃれ着感覚で着る着物ですので、格式ある袋帯の代わりに錦織りや箔の入った豪華な名古屋帯を合わせるのも良いでしょう。名古屋帯は、半幅帯は浴衣と合わせることもできるので、色違いで2、3本持っているととても重宝します。
小紋の種類

小紋には江戸小紋や京小紋など大きく分けて5つの種類があります。その特徴と伝統的技法についてご説明します。
江戸小紋
江戸小紋は江戸時代から継承されてきた職人技が凝縮された着物です。細かい柄を染めるのに必要な「伊勢型紙」と呼ばれる型紙を彫り師が彫り上げ、次に染め師がひとつひとつ手作業で染めていきます。その技法はとても緻密で繊細なもの。
さらに、江戸小紋には鮫の肌のような柄が特徴の鮫小紋。細かな正方形を並べた角通り小紋。細かい霰を斜めに並べた行儀小紋があり、江戸小紋三役と呼ばれています。
なかでも「極鮫」と呼ばれる鮫小紋は、紀州徳川家の「定め紋」だったことから、格式の高い小紋として知られています
京小紋
京都は友禅の発祥地だったこともあり、華やかさが京小紋の特徴。京小紋は「型友禅」の技法で染められ、色の数だけ型紙を使います。 この友禅型紙を20枚から30枚、時には100枚を超えて使うこともあり、出来あがった京小紋は色彩も豊かで上品な華やかさがあります。
加賀小紋
加賀小紋には「加賀伝統小紋」と「加賀友禅小紋」の二つがあります。 「加賀伝統小紋」は江戸小紋のような細かい柄が特徴。「加賀友禅小紋」は友禅の技法が使われ、型友禅で染め上げたものです。 どちらにも共通しているのは、江戸小紋で使われている伊勢型紙が使われていること。 加賀小紋が江戸小紋と京小紋の合わさったものと言われているのはそのためです。
更紗小紋
更紗とは、室町時代にインドやジャワから日本に伝わったもの。最初は茶道具を入れる仕覆として伝わりましたが、江戸時代には日本風にアレンジされて「和更紗」と呼ばれるようになりました。 それから大正時代に帯として作られたのをきっかけに、着物の柄として染められるようになったようです。 エキゾチックな色合いと雰囲気は、さりげない異国情緒がただよう着物です。
紅型小紋
琉球王朝の礼服と使われていたのが紅型です。色は黄、紫、藍、緑を基調とし鮮やかさが眼を引きます。 色や柄の大きさによって着る階級が決まっていたそうで、大きな柄ほど身分が高いとされていました。 紅型小紋は柄がはっきりと浮かび上がるため、小紋のなかでも存在感があるデザインと言えるでしょう。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●の箇所は本日の日付です。
■の箇所は定休日です。